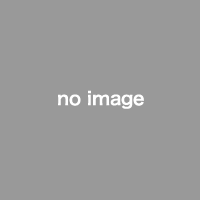第8回 第3部 ITをビジネスに活用する技術 3.4 IT以前の課題「働く人の心を繋ぐ」
第8回 第3部 ITをビジネスに活用する技術
3.4 IT以前の課題「働く人の心を繋ぐ」
「かんばん」は「ものづくり」の現場で働く人々の同期連携を図る方策の一つだ。しかし、独り歩きする幼児に似ている。発行すると、何か起きたとき、止められない。しかも、供給責任を背負っているので、働く人々にムリ・ムラ・無駄を強いる。
「かんばん」の目的に立ち返ると、働く人々の自律・協調・分散を可能にする簡易な方策がある。最終製品メーカの生産スケジュールをサプライヤ(自社工場を含む)に開示しよう。
生産進捗もスケジュールに上書きして開示しよう。スケジュール通りに作業が進行することは滅多にないので、若干の時間的余裕(Time Fence)を持たせて作業着手権限を与えることにしよう。そうすれば、「かんばん」なしの同期生産は容易だ。
ある期間(生産タイムフェンス)内の引取責任を確約すれば、発注指示や納入指示は不要だ。生産スケジューリングの意味を見直すほうがよい。スケジュール通りに生産活動できるほど現在の製造ビジネスは甘くない。刻々と変化する事態に合わせて素早く再スケジューリングすることが肝要だ。それは経営を支える「そろばん」に相当する。
第8回講義のテキスト&YouTube・URL
テキスト及びYouTubeを視聴される方は、読者登録をお願い致します。