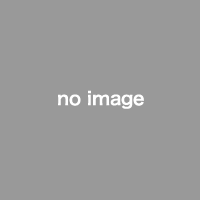第6回 改めて・いまなぜ概念データモデル設計か
第6回 改めて・いまなぜ概念データモデル設計か
情報システムを構築するとき、「利用者(多数)」と「技術・技能者」が一定の構想を共有する必要がある。
技術・技能は幾つもの分野に分かれており、様々な経緯で能力を習得している、そのままではまとまりにくい。
概念データモデル設計法の指導を通して、全体をまとめる役割を果たしていただきたい。
「My 概念データモデル設計法」を持つことが肝要です。完全なモデルはできあががらないことが多い。
構築の過程で分野毎に利用者と技術・技能者が共同で実現し、完成に近づける余地が必要です。
その過程で、沢山の指導者が生まれるなら、「成功」です。
第6回講義のテキスト&YouTube・URL
テキスト及びYouTubeを視聴される方は、読者登録をお願い致します。